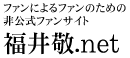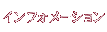インタビュー
必見対談!「福井敬vs能楽師・津村禮次郎」後半
(2007年8月28日 16:38)昨日に引き続き、「能楽タイムズ8月号」からの掲載です。
『言葉』について
津村 『日本語』……言葉について、お話をしましょうか。
福井 お能も基本的には肉声……生の声のみで表現しますが、オペラも原則的にはマイクなどを使わず、生の声でオーケストラに負けないように響かせる訓練をしています。昔は、マイクなどありませんからね。
西洋の音楽と古典の能……歌は違うのでしょうけれども、大元は同じですよね。
津村 響かせるテクニックなどの違いはあっても、根本は一緒でしょうね。
福井 現在、芸大で教えているのですけど、芸大の『邦楽科』の生徒が副科目として声楽を習いに来ていたのですが、皆さん、声帯が強いんですね。声が響きますし、いくら歌っても疲れませんね。そういう発見もあります。邦楽科の生徒は、西洋の発声に興味を持っているのか、意欲的にやっていますよ。逆にこちらも、いろいろと観察していますが、呼吸法は同じで、丹田に息を籠めて支えています。基本は東西ともに同じなんですね。本当に面白い(笑)。
津村 福井さんは、自然な歌い方をなさる。私は『創作』をやったり、新劇の人と一緒の舞台に出たりもしますので、いわゆる通常の謡そのものの発声では伝達しにくい場合も出てくるのですね。だから、少し、地の声に近く、クリアーな謡い方をするように努力しています。響きは良くても、言葉としてお客様に届かないと困りますから、考えながら謡うようにしています。謡には、響きとか、感情表現、雰囲気は入っていても、言葉の持つ意味合いをどれだけ伝えられるか、を考えています。能の場合は面を着けますから、それだけでも声がくぐもってしまう。日本語の解らない外国人は言葉が通じないので始めから問題ないですが、日本人だと、全部ではなくても言葉が解らないと苦痛になる。日本語の持つ美しさは残して行きたいですね。
一九九九年、新国立劇場の創作オペラ「罪と罰」は、原嘉壽子さんの作曲、まえだ純さんの台本で、この時、福井さんの日本語によるオペラを初めて聴いたんですが、言葉の明晰さには驚きました。これは個性なのでしょうかね。
福井 日本語で歌うテクニックがどうのと言うよりも、言葉の持っているドラマを聞いてくださる人に、どれだけ伝えなければいけないかということを意識するかしないかかも知れません。歌を歌として歌うのではなくて、歌なのだけれども、その中には自分の「想い」があるのですよね。その人が持っている気持として、それを発しなければならない、と思いますから、それを意識しながら歌っていますね。
津村 能の場合は、意識というか感情を籠めると、言葉が不鮮明になりがちになるのですが、想いを籠めつつ、音としてクリアーにしておられますね。
福井 そのように感じていただくと、とても嬉しい(笑)。
津村 少しも煩わしくなく聞こえました。日本の歌手なのですから、日本語で歌ってほしいなと思うんですよね。
福井 私も日本人ですから、日本語の歌を歌っていきたい。以前に、松本隆さんプロデュースのCDに入れさせていただいた「美しき水車小屋の娘」は、本来は、シューベルト作曲の、ドイツ語の歌詞の曲ですけれども、松本さんは、詩が自然な日本語になるように訳されたんです。聞かれる方は、音楽の中にドラマ……物語を聞いてくださるのじゃないかと思います。日本人が外国語の曲を聞く時はワンクッションあって、頭の中で理性が勝ってしまうのですね。感じたまま聞けるかというと難しい。
津村 それが日本語で歌われると、歌っている方と、パフォーマンスの方と、観客が、ドラマと同時進行で行けますよね。
埼玉の初演、東京での再演を拝見したのですが、一時間ほどを暗譜で、素晴らしかったですね。
福井 お能も暗記するのですから大変ですね。
津村 似ている文句が多いですから、年を取ってくるとグチャグチャになったりして(笑)。
福井 西洋の音楽界では、日本の能の精神がもてはやされています。「隅田川」から作られたブリテンのオペラ「カーリュー・リバー」は能そのものですね。
津村 お歌いになられたのですか。
福井 いえ、まだやっていません。
津村 お聞きになったことはありますか。
福井 ええ。演出も能的でした。西洋の音楽で、能的な舞台を作っていくのも微妙ですが、逆に、そういう形も面白いなと感じました。
津村 私がオペラに関わったものですと、三年前にバルトークの「青ひげ」をダンスオペラの形で、愛知芸術劇場のプロデュースで参加しました。指揮者はハンガリー人で、ダンスはイタリー人のアレッシオ・シルベストリンと白河直子さんでした。「青ひげ」は、歌手二人だけの、一時間足らずのオペラですけれども、そこに、城の精霊という形でキャラクターを作ってくれました。冒頭の吟遊詩人の語りと舞というか所作は全編にからむのですが、その中で、声は「ウォーッ」と出すだけなのですが、舞台に出たり入ったりするんです。面を着けてですから、これは大変でしたね。特に困ったのは出入りのタイミングでした。
キッカケと『コミ』
福井 タイミングは、どこで取ったのですか、音楽で?
津村 舞台のデレクターが指示を全く出さないので音楽で覚え、自分でカウントしてきっかけを取りました。まあ、何とかなりましたけれどね。タイミングの取り方で、ダンサーの人と同時に動く箇所があったのですが、我々は『コミ』といって、『間』を取るのが習性になっているんですね。同じタイミングを取るのですが、コミの分が必ず遅れてしまう。一拍前にタイミングを合わせないと駄目だというのを発見しました(笑)。
福井 なるほど(笑)。
津村 発声の場合は、どうですか。
福井 声を出すためにはブレスが必要ですから、歌い出す前には、ブレスが大事になります。ドラマによってはブレスも変わるでしょうし、呼気と吸気の関係ですね。能の場合は、いかがですか。
津村 吸い込んで、どのタイミングで声にしていくかですね。まず役柄や情景の気持を作って、息を吸い込み、声にして出して行く。謡に限らず、舞う時も同じで、序之舞のようにゆったりとした舞ですと、タイミングが長いですから、長く取りますが、あまり、それに囚われずに出た方がいいなと最近は思います。
福井 『コミ』ね、解るような解らないようなものですが(笑)。ブレスにも、いろいろあって、『ヴェルディ・ブレス』と呼ばれるものは、吸気が声として出てしまう。テンションを上げて、息を体に貯めますから、これが『コミ』に近いのかな(笑)。呼吸法もでしょうが、しっかりとした謡は、腰が立っていますね。
津村 昨年、北欧の帰りに、パリのオペラ座に行き、少年達を指導している人と知り合いまして、オペラ座のバレースクールを見学させてもらったんですよ。彼はフランス人なのですが、日本で柔術やお茶を嗜んでいたんですね。そういう経験を十二歳から十八歳ぐらいの生徒の授業に取り込んでいるんです。「アン・ドゥ・トルァ」の代りに「一・二・三」と(笑)。
子供たちの構え……立ち姿が反りすぎるんです。「こうしなさい」と指導するのを見ると、舞の構えと同じなのです。少し前傾斜で両腕のふところを深く構えるのです。
福井 軸をきちんと作って歩くのも同じなのでしょう。
津村 体を、どう使って表現するかは万国共通なのでしょう。
この間は、コンテンポラリーダンスの大島早紀子さんが演出のオペラ「ダフネ」をされましたね。神話の世界の物語で「アポロ」を歌われて、演出も興味深かったです。
福井 凄く新鮮で楽しかったですね。私たちは歌で表現しますが、ダンスは身体で全てを表現する。表現の仕方は違うのですけれども、そのためのテンションが凄いんですよ。自分の体を百二十パーセント使って表現する。私たちの歌と同じだなと感じました。やはり『軸』が必ず同じ所にあります。違った発見もありますが、同じ部分の発見もあって、お客様に伝えるということを再認識しました。
あれだけダンスと融合した形でのオペラ公演は初めてだと思います。
津村 神話の世界が現出しましたね。
福井 津村さんは、いろいろな試みをなさっておられますが、数多いでしょう。
津村 多いですね。二〇〇五年に致しました「ある母の物語」というのは、アンデルセンの童話で、デンマークの音楽家、ヤコブ・ドラミンスキーという、能も好きな人がデンマーク語で書いて、英訳、日本語訳を作ったんですね。デンマークで、子供のためのオペラを歌っている、バリトンとソプラノ歌手と、大鼓と小鼓は日本の囃子で、笛や効果音はコンピュータ音楽を使いました。全体はデンマーク語で歌いますが、私は母親の役で日本語でした。地謡と歌手たちが重なる部分は、地謡はカタカナでのデンマーク語で謡ったのです。これは日本の能楽堂で催した時の写真です。子供が病気になって、旅人におもてなしをしている間に、子供がいなくなってしまうのですね。実は死神が連れて行ってしまった。それを母親が、いろいろなバリアをクリアーして追いかけて行く。途中に茨が立ちはだかっていたり、湖があったり、夜の女王がいたりして、枯れた茨を流した血で蘇らせたり、涙を流したあとの目が真珠になり、それと交換に湖を渡って、最後に死神と出会う。連れ去られた子供たちは、皆、花になっているのですね。その心臓の音を頼りに自分の子供の花を見つける。ところが、その花を取り上げると、別の子が死ぬことになる。デンマーク語がベースですので、所作や音楽など、各所にキューが入ります。これが大変でした。日本初演のあと、コペンハーゲンで公演しました。死神が「お前の目を返してあげよう」という場面で、母親が自分の目を受け取る所なのですが、デンマーク語は全く解りませんので、タイミングに苦労して、この箇所だけは英語で「EYES」と言ってもらいました(笑)。
福井 物語自体が、能の題材ですね。同時に「隅田川」も演じられたのでしょう。
津村 ええ、母親と子供の悲劇という意味で比較させたのです。この写真は「白足袋」ですが、コペンハーゲンの時は死神は「黒足袋」、夜の女王役・庭番は「グリーン足袋」を履きまして、ナショナル・ライブラリーのホールに、黒いボードの裸舞台を設営して、橋掛りも松も置いたんです。橋掛りに揚げ幕を吊ったのですが、幕の後方がオープンなんです。「幕の後側も見せたい」と言うんですね。我々は幕の後は「鏡ノ間」で、観客にお見せすることはありませんが、彼は、揚げ幕の内外で世界が変わるという能の演出を見せたい、ということでした。
福井 『子供向け』というのではないのでしょう。
津村 一般向けで、一時間半くらいの作品です。外国での演じ方は、伝統的なものを、そのままお見せする方法と、演出家が入って、違う観点から能を見せるのも一つの方法かと思います。
福井 会場によって、それなりの方法を採ればいいですね。日本人の発想だと、ある程度、決まってしまいますからね。今はオペラの世界でも、普通の演出は平凡だ、もっと壊していかなくては駄目だ、と前衛的な手法が採り入れられています。それをしないと、お客様が納得されない状況になって来ています。「蝶々夫人」も、原爆投下後の設定にするなど。
津村 連れ去られた子供たちが花になる場面では、後見役のデンマーク人が、紋付・袴で、葛桶に入れた造花を舞台に撒くのですけれども、こうした発想も国内では出ませんね。
福井さんの、今後のご予定をお聞きしましょうか。
福井 九月に、上野の東京文化会館で『二期会』で、ヴェルディの「仮面舞踏会」を上演いたします。津村さんは?
津村 八月は薪能が多いですね。長野、佐渡、小金井と続きます。佐渡が島では、今、盛んにイベントを考えています。ご存じのように、佐渡にはたくさんの能舞台がありますが、それらが衰退していかないようにと、再生を願って「トキ」という能も上演します。
福井 素晴らしいですね。今のような時代こそ、能のような精神世界を大事にして行かなくてはなりませんね。
津村 「古典は、やはり素晴らしい」と言っていただきたいですね。
能楽タイムズのご購入は、以下までお電話下さい。
株式会社 能楽書林 TEL 03-3264-0846
※「能楽タイムズ」1部400円(+送料)、年間購読5000円(送料込み)